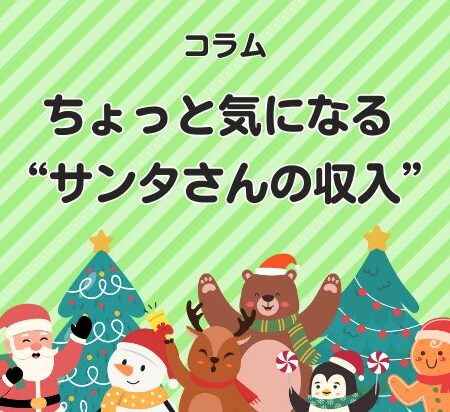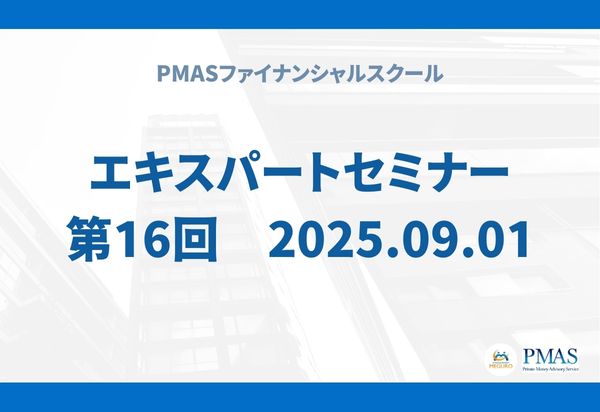定年を迎えると、家計の支出を見直す大きなタイミングが訪れます。
中でも「保険の整理」は、多くの方が後回しにしがちなテーマです。
前回は医療保険・がん保険の見直しポイントをお伝えしましたが、
今回は「死亡保険の整理」に焦点を当ててご紹介します。
家族に負担をかけず、賢く保険料を節約する方法をチェックしましょう✨
Contents
️死亡保険(終身保険・葬儀費用等)の整理
現役時代は、万が一に備えて手厚い死亡保障が必要でした。
しかし、定年を迎え、子どもが独立している場合、
高額な死亡保障は不要になるケースが多くなります。
本来は定年前から適宜見直しをして無駄を省くのが理想ですが、
殆どの方は後回しにしており、
定年というキッカケで見直しを考える方が多いので今回問題提起をしています。
とはいえ、葬儀費用の準備や、相続対策としての保険活用は引き続き有効です。
保険は「備える」だけでなく、「ムダを省く」視点も大切にしましょう。

①不要な死亡保障(定期保険)は解約・減額して保険料を節約
💡理由:子どもが経済的に自立していれば、大きな保障は必要ない
定期保険は、一定期間のみ保障が続く保険で、
掛け捨て型が多く、年齢とともに保険料も上がっていきます。
定年後は収入も減少するため、保障内容と支払いのバランスを見直す絶好のタイミングです。
先述の通り、子どもが経済的に自立していれば、大きな保障は必要ないことがほとんど。
60歳男性が定期保険(10年更新型)で1,000万円の死亡保障を契約していた場合
| 保障額 | 月額保険料(概算) |
| 1,000万円 | 約13,000~15,000円 |
| 500万円 | 約6,500~8,000円 |
| 300万円 | 約4,000~5,000円 |
※保険料は一例であり、詳しくはご相談ください。
このように、保障額を半分にするだけで
月々の保険料が6,000円〜10,000円近く安くなるケースがあります。
②残す場合は、葬儀費用300万円前後の終身保険に切り替え
💡理由:終身保険は、一生涯保障が続くため
どうしても「家族のために何かは残しておきたい」と思う方には、終身保険の活用がおすすめです。
- 終身保険は一生涯保障が続くため、葬儀費用などに確実に備えることができる
- 目安は300万円程度。このくらいあれば、一般的な葬儀費用はまかなえる
- 保険料も一生涯払うタイプではなく、短期払い型で老後の支出も抑えられる
その際の終身保険加入のポイント(考え方)は2つです(これが大事です)
- 退職金がない、もしくは、まとまったお金がない場合は、月払で保険に加入。
- 退職金の一部(目安は300万円以上)を保険料に充てることができる場合は、
「米ドル建て一時払終身保険」(定期引出タイプ)がお勧めです。
例えば、将来の葬儀資金準備のために、
今手元にあるお金で「米ドル建一時払終身保険」に加入します。
そうすると約12万円が定期引出金として毎年手元に戻ってきます。
(※メットライフ生命の2025年9月の利率で算出)
イメージとしては、手元資金を銀行に預ける代わりに、生命保険料として保険に加入することで、毎年利息のように定期引出金を受取ることができます。
もし現金が必要になれば途中解約してお金を戻すことも可能です
(※為替変動により300万円を割って戻る場合もあります)
③相続対策で「一時払い終身保険(非課税枠活用)」も選択肢
💡理由:保険にしておけば相続税を減らせる可能性があるため
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税枠があるため、相続対策としても活用可能です。
出典:国税庁ホームページ「相続税の課税対象になる死亡保険金」
- 預貯金を相続すると相続税がかかる場合でも、保険にしておけば相続税を減らせる可能性がある
- まとまった資金がある方は、一時払いの終身保険で保険金を指定した相続人にスムーズに渡すことができるため、相続トラブルを防ぐ意味でも、有効な選択肢。
生命保険を使って相続対策を行う目的として、税金対策は勿論ですが、それとは別に
「保険金受取人を指定することでお金を渡したい人に直接渡せる」というものがあります。
いわば「お金に宛先を付けることができる」といった感じです。

📝まとめ
定年後の保険は、目的を見直し、本当に必要な保障に絞ることが老後の安心と節約につながります。
見直しの際は、IFAであるPMASの目黒にぜひご相談くださいね。
スッキリとした保険設計で、安心のセカンドライフを送りましょう✨